妊娠8か月頃になると、お腹も大きくなり、ママの体も大変な時期。そんな中、上の子も下の子も「赤ちゃん返り」が始まると、対応に悩むことが増えますよね。
「どうしてこんなに甘えてくるの?」
「わがままがひどくなった気がする…」
今回は、上の子と下の子の赤ちゃん返りの原因と、私がやっている対応策について詳しくご紹介します。
赤ちゃん返りは「成長の証」!まずは受け止めよう

赤ちゃん返りは不安のサイン
赤ちゃん返りとは、「自分も赤ちゃんに戻りたい!」という気持ちからくる行動です。上の子も下の子も、「ママが赤ちゃん(お腹の赤ちゃん)ばかりに気を取られてしまうかも…」という不安を感じています。
特に、妊娠後期になるとママが疲れやすくなり、自然と子どもにかける言葉や態度が変わることも。その変化を敏感に感じ取って、「もっとママに甘えたい!」という気持ちが強くなるのです。
実際に、上の子は、「赤ちゃんのお世話する!」と意気込んでいますが、「ママ抱っこちてほち〜」と赤ちゃん言葉を使ってみたり、指しゃぶりをするようになりました。下の子も、おむつを履きたがったり、抱っこをせがむことが多くなりました。
まずは共感!「ダメ!」と言わずに寄り添う
モンテッソーリ教育では、「子どもの気持ちを否定しない」ことを大切にしています。赤ちゃん返りの行動を「ダメ!」と止めるのではなく、「そうだね、ママに甘えたい気持ちがあるんだね」と共感してあげることが重要です。子どもにとって「ママは自分の気持ちをわかってくれている」と感じることが、安心につながります。
始めは子どもたちの変化が赤ちゃん返りとは気づかず、なんで、おむつを履きたがるのだろう?なんで、ベビーカーに乗りたがるんだろう?と疑問に思っていました。しかし、赤ちゃん返りが始まったんだと認識するとさみしいんだな、不安なんだなと共感して、こどもたちが求めてくることを否定することはなく可能な限り受け入れるようにしています。
子どもが自信を持てる環境
1.上の子への対応

「お手伝い」を増やして役割を持たせる
モンテッソーリ教育では、「子どもには自分でできることを増やすことで、自信を育てる」という考え方があります。赤ちゃん返りをしている子どもに対しては、「ママの小さな助っ人」として役割を持たせるのが効果的です。
実際に、最近わが家でも上の子が「料理を手伝いたい」「皿洗いをしたい」と言うようになりました。最初は「本当にできるかな?」と少し心配でしたが、よく考えると「ママを助けることで、自分の存在を認めてほしい!」という気持ちの表れなのかもしれません。そこで、片付けの時間を私たち二人だけの特別な共同作業時間として位置づけ、一緒に取り組むようにしました。
お皿を一緒に洗ったり、テーブルを拭いたりするたびに、「〇〇がいてくれて本当に助かったよ」「ママ、一人だったら大変だったから、すごく嬉しいな」と伝えるようにしています。こうすると、子どもの表情がパッと明るくなり、「またやりたい!」と意欲的になってくれます。子ども自身が「自分は役に立てるんだ!」と実感することで、自信につながり、赤ちゃん返りの不安が少しずつ和らいでいくのを感じます。
スキンシップを増やす
上の子も赤ちゃんが家に来るということがどういうことか理解をしていることと思います。お手伝いも頑張ろうとしているし、自立をしようと頑張っています。しかし、小学校入学や赤ちゃんが増えることに対して不安を感じている部分があるのだろうなと思います。「もうお姉ちゃんだから」と甘えを制限するのではなく、意識的にスキンシップを取ることが大切です。ぎゅっと抱きしめたり、一緒に遊ぶ時間を作ることで、愛情を再確認できます。下の子がいるとなかなか自分ひとりだけの時間を取ることができないので、たまに2人だけでお散歩に出かけたり、ゆっくり座って話を聞いたり、その子だけの時間を作るようにしています。
2.下の子への対応

「たった5分」でOK!ママと子どもだけの時間を確保
赤ちゃん返りが起こるのは、「ママが自分を見てくれない」と感じているから。1日の中で子どもたちそれぞれに意識的に時間をつくると、子どもの気持ちが安定しやすくなります。
下の子は上の子よりも早く起きるのでその時間帯を特別時間として、抱っこをしたり、一緒にソファに座ってゆっくりしたりスキンシップをしています。日によってはママだったり、パパだったり2人だったりするので、気分に合わせて対応しています。とにかく「大好きだよー!」と伝えるようにしています。
たった5分でも、「ママは自分のことを大事に思ってくれている」と感じることで、子どもの心は落ち着きます。
生活リズムを整える
赤ちゃん返りによって生活リズムが乱れることもあります。特に今は春休みで、つい家でのんびり過ごしがち。そうなると寝る時間も遅くなり、さらに赤ちゃん返りが強くなることがあります。
そこで、お天気の良い日はなるべく外に連れ出し、しっかり遊ばせることで適度に疲れさせるように意識しています。幼稚園が終わる時間帯くらいに帰宅し、そこからはいつものルーティンを崩さず「晩ご飯→お風呂→絵本」の流れで就寝へと誘導。リズムを整えることで、気持ちも安定しやすくなります。
ただし、疲れすぎると逆に赤ちゃん返りが激しくなることも。遊びの時間や刺激の量を見極めながら、子どものペースに合わせた対応を心がけています。
まとめ

赤ちゃん返りは「愛情を確認したい」サインです。モンテッソーリ教育の視点で、「共感する」「子どもが求めることを可能な限り受け入れる」「お手伝いで役割を持たせる」ことで、上の子も安心しながら成長できます。子どもの気持ちに寄り添いながら、家族みんなで新しい赤ちゃんを迎える準備をしていきましょう。
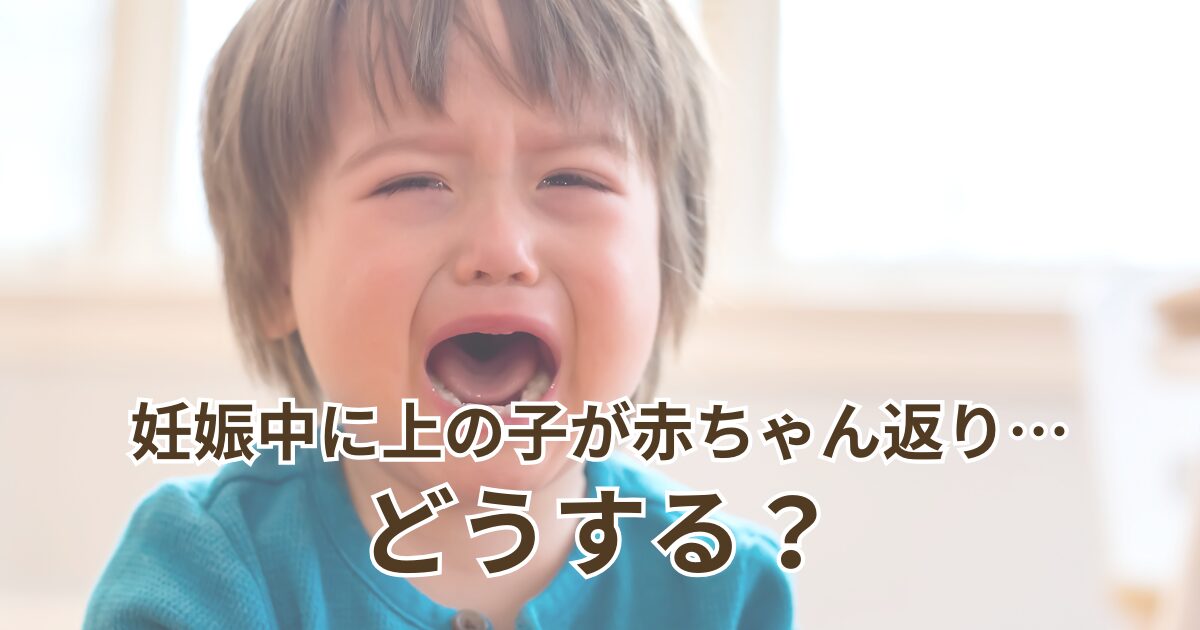

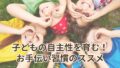
コメント