仕事から帰ってきてバタバタな夕方。「早くしてって何回言えばいいの?」「おやつ食べたら洗い物出してって言ったよね?」「なんでまだ準備できてないの!?」…つい言いたくない言葉が口からこぼれる。そんな自分に自己嫌悪する夜。
私もかつてはそうでした。でも今では、夕方のルーティンが子どもと一緒に回るようになり、笑顔で眠れる日が増えたんです。そのカギは、「環境」と「任せること」。モンテッソーリ教育の視点から、夕方ルーティンがうまく回らない理由と、子どもが自然と動き出す仕組みをご紹介します。
どうして子どもは“動かない”のか?
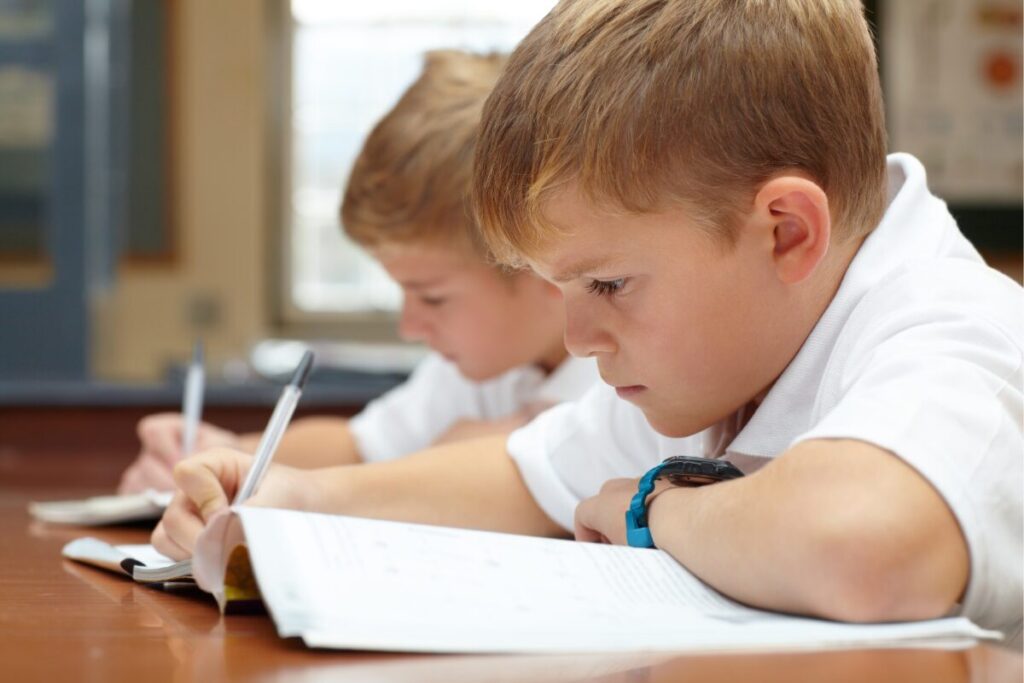
子どもにとっての「夕方」はフルマラソンのゴール
夕方、親にとっては「ここからが本番」。仕事モードから一気に家庭モードへとギアを入れ直す時間です。けれどもその一方で、子どもにとって夕方は、一日がんばったあとの“燃え尽きゾーン”でもあります。園や学校では、人間関係の中で気をつかったり、集団生活のルールに従って行動したり、小さな我慢をたくさん重ねたりと、大人が思っている以上にエネルギーを使っています。そんな一日をようやく終えて、子どもが「自分に戻れる時間」が、ちょうど家に帰ってきたこのタイミングなんです。だからこそ、帰宅してすぐに「お風呂!」「ごはん!」「明日の準備!」と次々タスクを求められるのは、子どもにとっては大人が想像する以上にハードルが高いことなんですね。
命令されるとやる気はなくなる
「今すぐ○○して!」「なんでやらないの?」つい言ってしまいがちな言葉ですが、これらは子どもを“自分で考える力”から遠ざけてしまうんです。モンテッソーリ教育では、“自分でやりたい”という内発的な意欲こそが、行動の原動力と考えます。命令よりも、「選べる環境」「自分で決められる流れ」があると、子どもは動き出します。どっちをする?
子どもが“動く仕組み”のつくり方

その日の流れに合わせて、就寝時間も“ゆるやかに調整”
わが家では、帰宅後に子どもたちがホッとひと息つけるように、まずは30分ほどの自由時間をとるようにしています。テーブルの上には軽いおやつ(フルーツなど)を用意しておき、食べたい子は食べる、遊びたい子は遊ぶ、スクリーンタイムを楽しむ子もいて、それぞれが思い思いに過ごせる時間です。その際、「タイマーが鳴ったらお手紙と汚れものを出してね」と声をかけておき、私はその間に夕食の準備を進めています。タイマーを使うことで、切り替えもスムーズになりました。また、習い事などで帰宅が1時間ほど遅くなる日もあります。そんなときは自由時間を短縮し、就寝時間を遅らせるなど工夫しています。時間にとらわれすぎず、その日の予定や子どもの様子に合わせて、柔軟にスケジュールを調整することが、イライラしすぎないコツだと感じています。
やることを“目に見える”ようにする
「次は何するんだっけ?」「言われてもピンとこない」これはよくある子どもの声です。
そこでおすすめなのが、ビジュアルスケジュールの導入。
- 夕方の流れを1枚の紙にイラストで表す
- マグネットやチェック式で「終わったら動かせる」工夫をする
- 【例】洗い物出す→ご飯→はみがき→お風呂→トイレ→絵本→寝る。こうすることで、「今どこ?」が一目でわかる。“やらされてる感”から“自分で進める達成感”に変わります。
お手伝いは“戦力”よりも“やる気スイッチ”
お風呂掃除なんて余計に時間かかるだけ…。そんな声も聞こえてきそうですが、実はこれが子どもが自分から動く最強の仕掛け。子どもは役に立ちたいという気持ちを本能的に持っています。モンテッソーリ教育では、3歳からすでに“共同生活の一員”として扱います。つまり、“子どもでもできることを信じて任せる”ことで、自尊心が満たされ、次の行動にも自分から動き出せるんです。
我が家が変わった!リアル体験談

当時は地獄…毎晩が怒鳴り声だった
当時の私はフルタイム勤務。保育園のお迎えは18時前、帰宅してからご飯を作って…という流れに、イライラは限界突破。「どうして今すぐやらないの?」「ちょっとは手伝ってよ!」怒っても動かない → さらに怒る → 自己嫌悪。このループに苦しんでいました。
仕組み化でガラリと変わった
モンテッソーリの考えを知ってから、私は子どもとの関わり方を少しずつ見直していきました。見える形でスケジュールを示すようにしたり、お手伝いは最初から「任せる」ことを前提にしたり、「早くして!」ではなく「どっちからやる?」と声かけの仕方を変えてみたり。
そんな小さな変化を積み重ねていくうちに、子どもにも驚くような変化が現れました。毎日繰り返していくうちに、流れを自分で理解し始めて、こちらが何も言わなくても自然と動けるようになってきたのです。
もちろん、気分が乗らない日もあります。でもそんなときでも、「は〜い…」とだるそうにしながらもやろうとする姿勢が見られるようになり、それもまた成長だと感じました。
さらに、本当にやりたくない日は、「今日は疲れてるから、お母さんがやって〜」と、きちんと理由を言葉にして伝えられるようにもなってきました。
そんなとき、私たちの合言葉は「チームワーク!」。無理をせず、「じゃあ今日はママがやるね」と私も素直に協力するようにしています。
その結果、以前のように怒ることなく、寝かしつけまでスムーズにいける日が少しずつ増えてきました。そんな夜は、ただただうれしくて、心から「今日はよく眠れそう!」と思えるようになったんです(笑)。
まとめ:夕方のカギは「環境」と「信じて任せること」

仕事終わりの夕方は、親にとっては体力も気力もギリギリ。でも子どもにとっても、“頑張った1日を終える大事な時間”。だからこそ、親が頑張るのではなく、“仕組み”に助けてもらうことが必要です。
最後にもう一度、今日のポイントをまとめます👇
・子どもが動かないのは“疲れ”と“見通しのなさ”が原因
・命令ではなく「自分で決められる流れ」をつくる
・ビジュアルスケジュールで“今どこ?”を可視化
・お手伝いは“戦力”より“やる気スイッチ”として活用
・イライラする前に“仕組み”を整えることが最強の解決策
「早くして!」じゃなくて「どうやって一緒にやる?」に変えたら、夕方のバタバタは“親子の信頼タイム”に変わります。あなたの家庭にも、笑顔の夕方が増えますように。


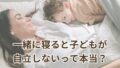
コメント