「そろそろオムツ、外した方がいいのかな?」そんなふうに思い始めたとき、まわりのママ友やSNSの声が気になって不安になることはありませんか?
私自身、1人目の子育ての時はテキスト通りに進めなければという気持ちが強く2歳までにはオムツを取るぞ!と意気込みすぎて、子どもに対してすごく厳しかったなと後悔しています。トイレトレーニング、いわゆる「トイトレ」は、子どものペースと向き合う繊細なテーマ。焦れば焦るほど、うまくいかずにお互いストレスになってしまうものです。
この記事では、モンテッソーリ教育の考えを取り入れながら、オムツを外す時期やトイトレの進め方について、私自身の体験をもとにわかりやすくまとめました。今日からすぐにできるヒントも紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
オムツが外れる「本当の時期」とは?

平均年齢は2歳〜3歳。でも個人差が大きい!
一般的には、オムツが外れるのは2歳半から3歳ごろと言われています。しかし、実際には1歳半ごろからパンツに移行する子もいれば、4歳を過ぎてもオムツを使っている子もいます。モンテッソーリ教育では、子どもの成長には一人ひとり異なるリズムがあると考えます。そのため、「〇歳になったからトイトレを始めなければ」といった基準ではなく、子どもが自ら「やってみたい」と感じたタイミングを大切にするのが基本の考え方です。
こんなサインが出たら、トイトレのチャンス!
子どもがオムツから卒業する準備ができたときには、いくつかのサインが見られることがあります。たとえば、排泄のあとに不快感を示したり、大人のトイレに興味を持ち始めたりします。また、朝起きたときや昼寝のあとにオムツが濡れていない時間が増えてきた、あるいは「うんち出た」や「おしっこ出る」と言葉で伝えるようになったら、トイトレの始め時かもしれません。
トイトレはするべき?しないとダメ?

「教える」より「環境を整える」がモンテッソーリ流
モンテッソーリ教育では、「教える」ことよりも、「学べる環境を整える」ことが大切とされています。これはトイトレにも通じる考え方です。
たとえば、子どもが自分で使えるサイズの補助便座やおまるを用意したり、トイレを落ち着いた安心できる空間に整えたりすることで、子どもが自然と「自分でやってみたい」と思えるようになります。また、自分でズボンを上げ下げしやすい服を選ぶことも、子どもが「できた!」という成功体験を積むためにとても効果的です。
やらないとどうなる?焦りは逆効果!
「同じ月齢の子は、もうオムツが外れてるよ」と耳にすると、どうしても焦ってしまいますよね。私もそうでした。「うちの子だけ遅れているんじゃないか」「早くしなきゃ」と、気持ちがどんどん急いてしまって、、、。
実際、上の子のときは、その焦りから無理にトイトレを始めてしまいました。その結果、失敗を怖がるようになり、排泄そのものを我慢するように。次第に便秘がちになってしまい、最終的には慢性的な便秘に。毎日排便のたびに苦しむようになり、便秘薬を使わなければならない日々が続きました。
「本当に、ここまでしてオムツを外す必要があったのかな?」当時の私は、それが子どもの心と体に与える影響の大きさを、きちんと理解できていなかったんです。あとになって深く後悔しました。
その後、幼稚園に通うようになってからは、特別なことをしなくても、自然とオムツが外れていきました。周りの友だちと一緒にトイレに行く日常の中で、自分から「やってみよう」と思えるようになったんです。気づけば4歳になる前には、オムツを卒業していました。「焦らなくても、子どもにはその子なりのタイミングがあるんだ」そう実感した瞬間でした。
ママも子どもも笑顔で進める!モンテッソーリ式トイトレの実践方法

ステップ①「観察」から始めよう
モンテッソーリ教育の基本は「観察」。トイトレを始めるときも、まずは子どもをよく観察することが第一歩です。
たとえば、いつ排泄しているのか、排泄前にどんな様子をしているのか、排泄後にどんな反応をしているのか。こういった日々の様子から、子どもの排泄のリズムや、トイレへの関心が少しずつ見えてきます。
実際に上の子の場合も、毎朝起きて30分後くらいに必ずおしっこをしていたため、タイミングを見計らってトイレに誘うようにしました。観察を重ねることで、「今なら成功しそう」というタイミングが自然とわかるようになります。
ステップ②「準備された環境」で子どもが主役に
モンテッソーリ教育では、「環境が子どもを育てる」と言われるほど、環境の整え方がとても大切にされています。トイレトレーニングにおいても、子どもが自分の意思で行動できるような環境を整えることが、成功への大きなカギになります。
我が家の場合、トイレに対して少し敏感になっていた時期がありました。そこでまず意識したのは、トイレを特別な場所にしないこと。子どもが「トイレに行きたい」と言ったときには、過剰に反応せず「あ、じゃあ行っておいで〜」と声をかけるだけにしました。トイレは当たり前に行く場所なんだよ、という空気を自然に作っていったんです。
逆に、トイレに行きたがらないときには無理に連れて行かず、「おしっこ行きたくなったら、次はトイレに行ってみようね」と、プレッシャーをかけずに伝えるようにしていました。するとある日、自分から「トイレ行く!」と言って、一人でトイレに行くようになったんです。自発的な行動を見たときは、本当に感動しました。
このとき、私が特に意識していたのは「失敗しても怒らないこと」。もしお漏らしをしてしまっても、「ぬれちゃったね。次はトイレ行こうね」と、やさしく声をかけるだけにしました。怒ったり叱ったりしてしまうと、子どもが自信を失ってしまうからです。
子どもが前向きな気持ちでトイトレに取り組めるように、心のサポートも環境づくりの一つだと実感しています。
【まとめ】
オムツ卒業に「正解の時期」はありません。大切なのは、子ども一人ひとりのペースを大人が信じて見守ることです。
モンテッソーリ教育の視点から見れば、トイトレは子どもの「自立」への大切な一歩。親が焦らず、観察し、そして適切な環境を用意することで、子どもは自然と自分のタイミングで成長していきます。私も何度も不安になりながら、子どもたちのトイトレを乗り越えてきました。だからこそ、悩んでいるあなたに伝えたいです。焦らなくて大丈夫です。おむつは、必ず取れます。子どもを信じて、そして自分自身も信じて、一歩ずつ進んでいきましょう。

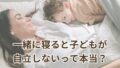

コメント