子どもが増えると避けられないのが「きょうだいげんか」。6歳と3歳の娘を持つ私も、毎日のように「やめて!」「嫌だ!」のけんかに悩まされています。ときには叩く、つねる、ひっかくといった暴力に発展することも…。そこで、今回は私が試しているきょうだいげんかへの対処法についてお話しします。
けんかは成長の一環!でも見守るだけではダメ

きょうだいげんかが起こる理由
きょうだいげんかにはさまざまな原因がありますが、大きく分けると次のようなものがあります。
- 自己主張のぶつかり合い:年齢が違うと理解度も異なり、思い通りにいかずイライラすることがある。うちの子たちは、遊びたい方法やルールが違ったり、テンションの温度差でけんかになることが多いです。
- 親の注目を引きたい:特に下の子が生まれると、上の子は寂しさを感じやすくなる。私がソファにくつろいでいたら上の子が膝に乗ってくると必ず下の子も乗ってきてそのままけんかに発展。そうなると私もゆっくりできないので、「けんかするなら、お母さん一人で部屋にこもります。仲直りしたら呼びに来てください」と言ってその場から立ち去ります。
- 遊びの延長でヒートアップ:楽しく遊んでいたのに、ちょっとしたことから本気のけんかに発展する。二人で遊んでくれてよかったーと思った瞬間、やだー!やめてー!の声とともにバシバシッと音が。そのたびに手を止めて二人のけんかを止めています。
ただ見守るだけでは危険?
「きょうだいげんかは成長の一部だから放っておけばいい」と言われることもありますが、
- 暴言や暴力に発展すると危険
- 力の差で一方が不利になる
- 仲直りの仕方を学ぶ機会を逃す
といったリスクがあります。そのため、親が適切に介入することが大切です。
きょうだいげんかの上手な止め方

暴言・暴力が出たらすぐに介入する
「叩かない!」「そんな言い方しないの!」と注意するだけでは、子どもには伝わりにくいものです。大切なのは、冷静に間に入ってストップをかけること。
- 子どもと同じ目線にしゃがむ
- 「痛いよね」「悲しいよね」と叩かれた方の気持ちを代弁する
- 「何か叩くような嫌なことがあったのかな?」と叩いた方の気持ちも尊重する
- でも、「暴力はいけないこと」と毅然と伝える
私は2人の娘に「あなたには人を傷つける権利はない」と常に言い聞かせています。癇癪を起こして止められないときはこの言葉を聞いていないこともありますが、いつか理解してくれると思い、言い続けています。
一人ずつ話を聞いて気持ちを整理
けんかの直後は興奮していて、冷静に話せないことも多いです。そのため、まずは気持ちを落ち着かせることが重要。
- それぞれの話を別々に聞く
- 「〇〇はどうしたかったの?」と質問して気持ちを整理する
- 相手の気持ちも伝えて、お互いの立場を理解させる
まずは、「今、お話ができますか?」と子どもたちの興奮度を確認します。泣いていたり、興奮していて話ができない状態の場合は「一人で思い切り泣いておいで。落ち着いたら何があったか話してね。」とまずは感情を出し切ってもらうようにしています。
きょうだいげんかを減らすためにできること

上の子の気持ちを大切にする
上の子は「お姉ちゃん(お兄ちゃん)だから我慢しなさい」と言われることが多いですが、それが不満につながることも。なので、その言葉は言わないようにしています。
- 上の子だけの時間を作る
- 「いつも助けてくれてありがとう」と感謝の気持ちを伝える
- 下の子ばかりを優遇しない
とにかく抱っこしてあげると落ち着くことができるのでまずは抱きしめるようにしています。お互いに善悪をつけるのではなく、すれ違いや勘違いから問題が発生していることを伝えるようにしています。2人の話を聞いているときに、お互いに笑いあっていつの間にか仲直りしていることも。私の気遣いは何だったのか。と思うことも多くあります。大体けんかは忙しい時間帯や見ていないときに発生するので、いったん手を止めて子どもたちと向き合い、お互いイコールの立場でしっかりと話を聞いてあげると問題解決の時間は早くなります。
ルールを決めて事前に伝える
けんかになる前に、家庭でのルールを決めておくことも効果的です。
- 「叩いたらおもちゃはおしまい」などのペナルティを決める
- 使いたいおもちゃは順番に使うルールを作る
- 仲直りの方法を一緒に考える
6歳の子はルールという観念を理解しているので、説明をしやすいですが、3歳の子は絶賛イヤイヤ期。そして、姉が使っているものすべてを同じように使いたい!ほしい!(姉のものもわたしのもの!と勘違いをしている小さなジャイアンです)の時期です。とにかくこの家にはルールがあるんだよ。と理解してくれるまで一貫して言い続けることに気を付けています。
まとめ
きょうだいげんかは避けられないものですが、親が適切に介入することで子どもたちが「気持ちを伝える力」「折り合いをつける力」を学ぶ機会になります。ある程度は私も介入しないようにしていますが、暴力や暴言が出たら冷静に止め、一人ずつ気持ちを聞くことで、子どもたちも次第に自己解決できるようになります。子育ては大変ですが、一緒に成長していきましょう!
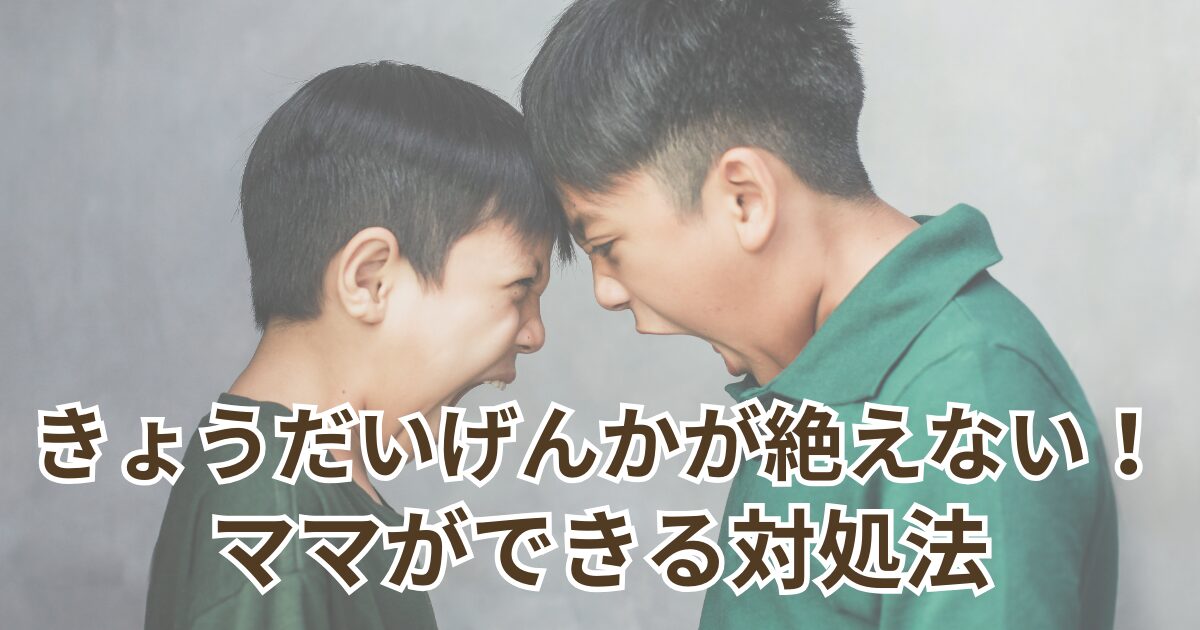


コメント