こんにちは、
6歳と3歳の娘を育てながら、現在3人目を妊娠中のママです。「子育てを楽しみたい」「でも現実はバタバタで余裕がない…」そんな日々の中、どうすれば穏やかな時間を過ごせるのか?を模索しながら、子育て・家事・仕事・家計と向き合っています。今回は、私が直面してきたリアルな育児の悩みと、それを乗り越えるヒントになったモンテッソーリ育児についてお話しします。
こんな方に読んでほしい
- 育児に悩みを抱えている
- 子育てをもっと楽しみたい
- 子どもの自立を促したい
- 子どもと一緒に穏やかな時間を過ごしたい
「乱暴」「片付けない」「テレビばかり」だった3歳児の変化

家族への暴力的な行動に悩んだ日々
娘が1歳半ごろから、イライラしたり、興奮したりすると家族に手が出るようになりました。何をしてもダメで、正直私も途方に暮れていました。そこで始めたのが、気持ちを代弁しながら叱るという方法。「○○したかったんだね。でも叩くのはダメ」と、感情を言葉で受け止め、代わりに噛んでもOKなタオルを渡すなど、発散の手段も用意しました。すると、2歳になる頃には感情の爆発が減り、言葉で伝えられるように。これはモンテッソーリの「自己表現の尊重」にも通じる考え方。子どもの「心」を見てあげることで、行動にも変化が現れることを実感しました。
片付けられないのは「環境」が原因だった
以前は「片付けなさい!」と怒ってばかりで、娘も嫌そうにしていました。でもモンテッソーリを学び、子どもの目線で考えるようにしました。子どもの目線の高さを測り、それぞれの目線に合わせた棚をそろえ、物の定位置(住所)を作り、「終わったら元の場所に戻そうね」とルールを丁寧に説明しました。すると、遊び終わると自らおもちゃを片付けるように!子どもが「できる環境」を用意することが、何より大切だとわかりました。
テレビ依存→タブレットに変更→ルール化で自分でオフ!
以前は私の準備を済ませるために朝からテレビをダラダラ見せてしまうことも…。モンテッソーリをヒントに「見る時間・見るタイミング」を明確にし、タイマーを使って「終わりの時間」を伝えるようにしました。最初は泣きながら反発していましたが、3日目には自分でタブレットの電源を切り「終わり」と言えるように。子どもは、大人が一貫していれば驚くほど順応してくれるんだと感じた瞬間でした。
指示待ち・自己主張できない娘が「言える子」に

「どっちがいい?」で選ぶ力を育てた
長女はとにかく控えめ。私が小さい時に教科書通りの育児をやっていたこともあり、人前で間違えることが怖くて、自分の気持ちを口にできない子でした。そんな彼女に毎日、「AとBどっちがいい?」という小さな選択肢を用意しました。選んだことを否定せずに「そっちにしたんだね」と共感するだけで、少しずつ「私はこうしたい」と言えるように。今では「週末は○○に行きたい!」と自分の希望も伝えてくれるようになりました。選ぶ経験の積み重ねが、自己表現につながったのです。
“励まし語録”で心の折れやすさに寄り添った
負けず嫌いで泣き虫な長女。負けると悔しさのあまり、物を投げてしまうことも…。でもよくよく振り返ると、私は「結果」しか見ていなかったことに気づきました。そこで、「がんばってたね」「最後までやったのすごいね」と“プロセス”をほめる言葉をメモ帳にストック。これを意識的に使うようにすると、少しずつ「悔しいけど、まぁいっか」と切り替える力がついてきました。気持ちを整理するために「泣きたいときは部屋で思いっきり泣いてもいいよ」と感情の出口も用意しています。
「何したらいいの?」からの脱却は“任せる勇気”
以前は毎朝、「次は何するの?」「早くして」と声をかけ続けていました。でも実は私が、子どもに考える余白を与えていなかったことに気づいたのです。それからは、私が先に起きて自分の支度を済ませ、子どもの準備につきっきりになる時間を作り、子どもには「今日は何からする?」と質問だけして、とことん準備を見守るように。最初は戸惑っていましたが、1週間もすると自分で考えて動けるようになりました。
まとめ|モンテッソーリで育児に自信が持てた
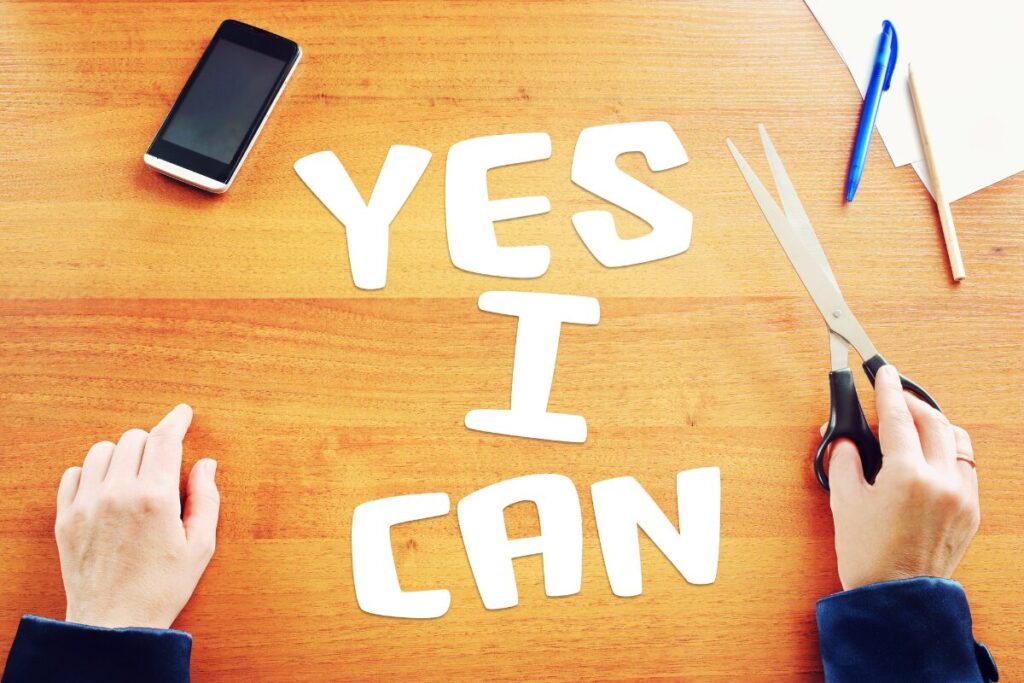
モンテッソーリを取り入れてから、私は「子育てはコントロールするものではなく、見守るもの」だと気づきました。もちろんうまくいかない日もあります。でも、子どもと信頼関係を築きながら一緒に成長していく感覚は、何より大きな喜びです。これから小学校入学、3人目の出産…とまだまだ私の育児は続いていきます。その過程もまた、ブログでお届けしていきますね。育児に悩んでいるあなたにとって、この記事が少しでもヒントになれば嬉しいです。
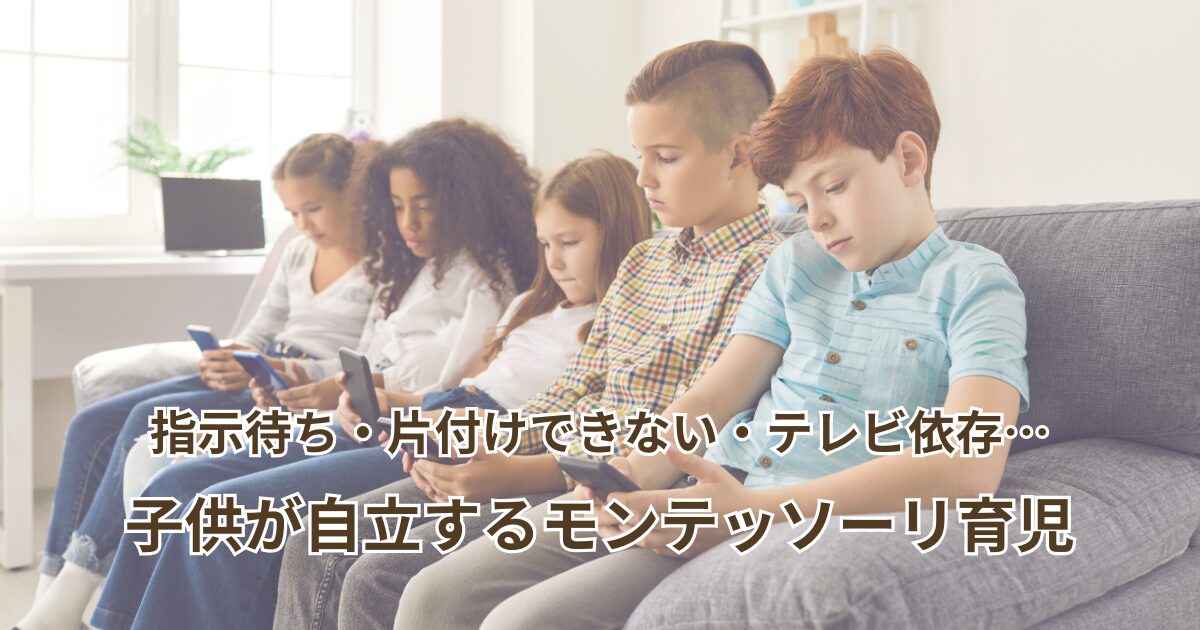


コメント